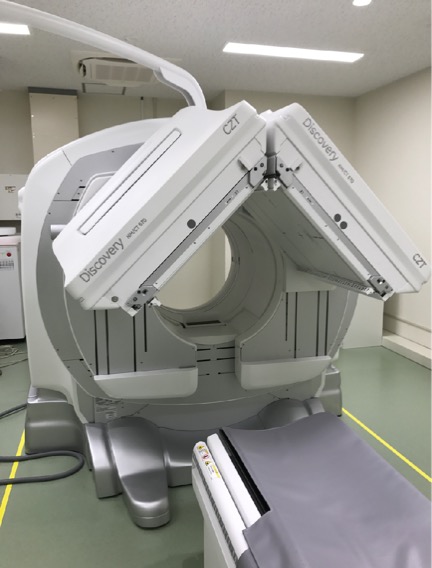脳神経内科・脳卒中内科

脳神経内科・脳卒中内科
Department of Neurology & Stroke Care Unit
多様な神経疾患の克服を目指して
エキスパートによるチーム医療で、患者さん一人ひとりに最善の医療を提供します
エキスパートによるチーム医療で、患者さん一人ひとりに最善の医療を提供します
NEWS
診療部長ご挨拶
脳神経内科は、1975年に初代の濱口勝彦教授が開設し、島津邦男教授、荒木信夫教授、山元敏正教授が引き継いできた歴史ある診療科です。
私たちの診療科では、基礎研究、臨床研究をもとに、「なおらない病気をなおす」をめざし、世界水準かつ最新の検査、治療、治験を積極的にとりいれ、神経難病の克服に挑みます。そして、「地域の先進医療の拠点」として、地域連携の推進、デジタル医療の併用などによる地域医療の充実を目指します。
そして何より、「すべては患者さんのために」をモットーに、多職種チームによる患者さん一人ひとりに寄り添った医療を提供します。とくに、パーキンソン病のデバイス補助療法、認知症・神経変性疾患・神経免疫疾患の抗体療法、小児神経疾患患者の成人後の移行期医療などに力を入れています。
当科受診希望の場合は、かかりつけの医師より、紹介状(診療情報提供書)をご用意していただきご受診ください。電話やFAXでの予約も可能です。
私たちの診療科では、基礎研究、臨床研究をもとに、「なおらない病気をなおす」をめざし、世界水準かつ最新の検査、治療、治験を積極的にとりいれ、神経難病の克服に挑みます。そして、「地域の先進医療の拠点」として、地域連携の推進、デジタル医療の併用などによる地域医療の充実を目指します。
そして何より、「すべては患者さんのために」をモットーに、多職種チームによる患者さん一人ひとりに寄り添った医療を提供します。とくに、パーキンソン病のデバイス補助療法、認知症・神経変性疾患・神経免疫疾患の抗体療法、小児神経疾患患者の成人後の移行期医療などに力を入れています。
当科受診希望の場合は、かかりつけの医師より、紹介状(診療情報提供書)をご用意していただきご受診ください。電話やFAXでの予約も可能です。

大山 彦光 OYAMA, Genko
診療内容・専門分野
脳神経内科では、脳・脊髄・末梢神経・骨格筋の神経系のどこに障害があるのか、患者さんのお話をよくお聞きして、病気の性質を把握したうえで、診察・検査を行います。そのため初めて受診される患者さんの診察にはお時間がかかりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
主な症状
- 頭痛
- めまい
- 物忘れ
- 体が勝手に動く(ふるえる、ぴくつく、けいれんする、くねくねする、こわばる)
- しびれ
- 脱力、歩きにくい、物がうまく使えない
- 話にくい
- 飲みこみにくい
主な疾患
| 神経変性疾患 | パーキンソン病、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、皮質基底核変性症、脊髄小脳変性症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など |
| 認知症疾患 | アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症、正常圧水頭症など |
| 神経免疫疾患 | 多発性硬化症、視神経脊髄炎、慢性炎症性脱髄性神経根炎(CIDP)、ギランバレー症候群、重症筋無力症など |
| 脳卒中 | 脳梗塞など |
| 機能性疾患 | 頭痛、てんかん、自律神経・発汗障害など |
| 不随意運動 | 振戦、ミオクローヌス、舞踏運動、バリスム、アテトーゼ、ジストニア(痙性斜頸、眼瞼痙攣、書痙、ミュージシャンジストニア)、顔面けいれん、チック・トゥレット症候群など |
| 神経感染症 | 髄膜炎、脳炎、クロイツフェルト・ヤコブ病など |
| 筋疾患 | 筋炎、筋ジストロフィーなど |
専門外来・特殊外来
パーキンソン病外来
パーキンソン病は、脳内のドパミン欠乏により、手足のふるえ、動作緩慢、筋肉が固いなどの運動症状を中心にさまざまな症状がみられる疾患です。高齢化率の上昇に伴い、患者数は激増しています。対症療法として、お薬によるドパミン補充療法が有効ですが、進行期には薬の効果が早くきれたり、不随意運動が困る場合があり、ポンプ治療(レボドパプロドラッグ持続皮下注療法とレボドパ持続経腸療法)や脳深部刺激療法(DBS)といったデバイス補助治療が有効な場合があり、適切なタイミングでの検討が必要です。また、ふるえ(振戦)が問題となる場合は、収束超音波療法(FUS)も適応となります。当外来ではチーム医療で脳神経外科や消化器科と連携し適切な治療を提供します。頭痛外来
頭痛には、ズキンズキンとした拍動性の痛みを伴う血管性頭痛、頭重感を有する筋緊張型頭痛などいろいろありますが、頭痛の原因を明らかにし、病態に合わせて、さまざな内服薬や、予防の注射などを組み合わせて治療を行っています。また、頭痛にはストレスなど種々の誘因が関与しているので、誘因を除去するための日常生活におけるアドバイスや運動療法として頭痛体操の指導を実施しています。認知症外来(物忘れ外来)
人生100年時代を迎え、物忘れの患者さんも増えてきております。当科では、アルツハイマー病、レビー小体認知症、脳血管性認知症などの主な認知症疾患の診療にとどまらず、他の認知症性疾患(正常圧水頭症、プリオン病、脳炎など)も専門外来だけでなく一般外来でも診療を行っております。ご本人だけでなく、ご家族の方も相談を受け付けております。また、家族性アルツハイマー病の遺伝子診断外来も当院精神科、遺伝子治療部、中央検査部と連携しておこなっておりますのでご相談ください。当科では,従来の認知症外来の中に,レカネマブ,ケサンラ治療を希望される患者さんに対しての新たな専門外来「MCI外来」をこのたび設立致しました。
軽度認知機能低下(MCI)外来
認知症ではないが、若いころよりも認知機能が低下した状態を、軽度認知障害(MCI)といいます。アルツハイマー病によるMCIでは、アルツハイマー型認知症になる前のMCIの段階から、すでにアルツハイマー病の原因であるアミロイドβ蛋白が脳内にたまってくることが知られています。現在、アルツハイマー病によるMCIに対して、抗体を注射してアミロイドβ蛋白を取り除く抗体療法が開発されました。抗体療法を希望する場合は、MCI外来を受診していただくことで、治療の対象となるか相談できます。詳しくは以下のMCI外来の資料をご覧ください。
不随意運動外来
不随意運動とは、体が自分の意思とは関係なく動いてしまう症状です。不随意運動にはふるえ(振戦)、ぴくつき(ミオクローヌス)、くねくね動く(舞踏運動、アテトーゼ)、ぶん回すような動き(バリスム)、ねじれ・傾き(ジストニア)、ある動きをとめられない(チック)などがあります。不随意運動は、パーキンソン病、ハンチントン病、遺伝性ジストニア、トゥレット症候群、遅発性ジスキネジアなどさまざまな疾患が原因となります。不随意運動によっては、日常生活動作に生活に大きな影響を及ぼすことがあり、早期に適切な原因診断と治療介入が重要です。当外来では、詳細な問診や診察、血液検査、電気生理学的検査、神経画像検査などを行い、適切な診断を行い、薬物療法をはじめ、ボツリヌス注射、外科治療・集積超音波療法(FUS)、脳深部刺激療法(DBS)などの治療法を組み合わせ、個々の患者さんに最適な治療法を提供します。病気の説明と治療方法
パーキンソン病
症状
振戦(手足がふるえる)、筋強剛(体がかたくなる)、無動・寡動(動作が遅くなる)、姿勢保持障害(転びやすくなる)
頭痛
症状
頭痛(主に片頭痛、群発頭痛、緊張型頭痛などの1次性頭痛など)