内分泌内科・糖尿病内科
研修可能なサブスペシャリティー領域
以下の各機構・学会の専門医・認定医の取得が可能内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医、糖尿病内科領域専門医(糖尿病専門医)、高血圧専門医、肥満症専門医、動脈硬化専門医、甲状腺専門医など
診療部長等からのメッセージ
当科は埼玉エリアの多くの内分泌代謝・糖尿病患者を受け入れており、糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医などを取得するのに極めて恵まれた環境が整っています。また、血管障害や感染症、悪性腫瘍などの併発疾患の診断や治療に関わる機会も多いことから、一般内科医としてのスキルも身につけることが出来ます。
埼玉医科大学の理念に「優れた実地臨床医家の育成」が掲げられていますが、当科はさらに一歩踏み込んで、「リサーチセンスをもつ、優れた実地臨床医家の育成」を目指しています。臨床では未解決の分野が多々存在しており、患者さんにとってより質の高い医療を目指すためには、新しいことを見出す「リサーチセンス」が不可欠です。このような方針のもと、臨床研修、卒後教育を展開しています。
埼玉医科大学の理念に「優れた実地臨床医家の育成」が掲げられていますが、当科はさらに一歩踏み込んで、「リサーチセンスをもつ、優れた実地臨床医家の育成」を目指しています。臨床では未解決の分野が多々存在しており、患者さんにとってより質の高い医療を目指すためには、新しいことを見出す「リサーチセンス」が不可欠です。このような方針のもと、臨床研修、卒後教育を展開しています。
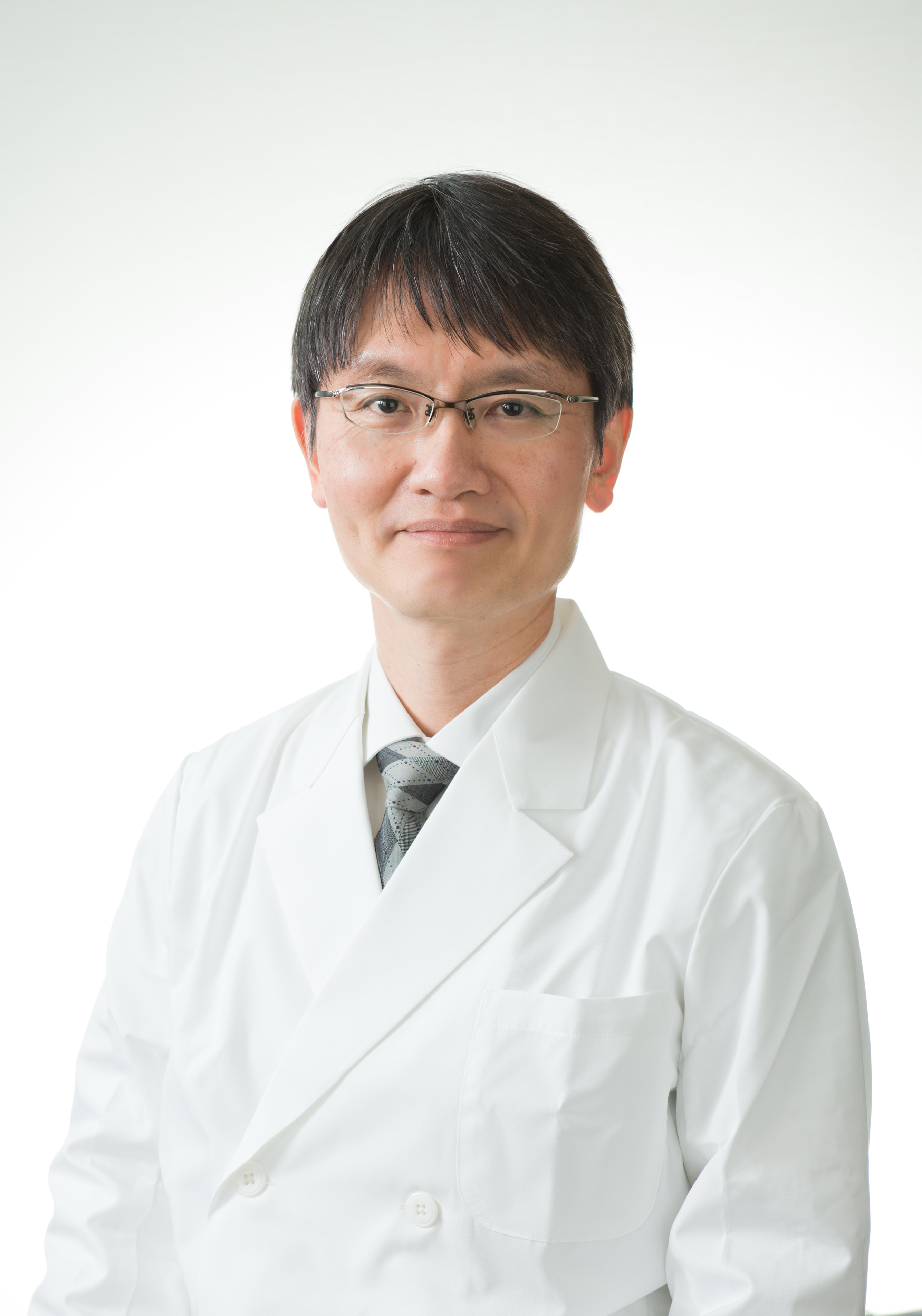 内分泌内科・糖尿病内科診療部長 教授 及川 洋一
内分泌内科・糖尿病内科診療部長 教授 及川 洋一
研修プログラム
研修プログラムの詳細は領域別専門医研修プログラムのページをご覧ください。概要・特徴
糖尿病・高血圧・脂質異常症などの非感染性疾患(Non-Communicable Diseases, NCDs)の増加に伴い、内科疾患のプライマリケアにおいて当科での研修の重要性がますます高まっている。当科は、埼玉県西北部の内分泌疾患や代謝疾患の診療の基幹施設として全国でも有数の患者数を有しており、糖尿病をはじめとするNCDsの診断と治療全般を体系的に修得することができる。また内分泌疾患の診断と治療についても、日常よく遭遇する甲状腺疾患から極めて稀な下垂体や副腎疾患を多数経験できる。さらには、最近注目されている骨粗鬆症についても、最新の診断と治療法を学ぶことが可能である。
現在、糖尿病や高血圧、脂質異常症の先進医療などにも力を入れており、先端的医療を提供できるよう努めている。
研修内容と目標
| 専門研修 | 卒後年数 | 研修内容と目標 | 資格等 |
| 1年目 | 卒後3年目 | 初年度から病棟、外来業務に従事する。内分泌・糖尿病疾患の初期対応を学ぶ。 | JMECC |
| 2年目 | 卒後4年目 | 提携病院に出向し、内科全般の診療を経験する。不足症例があれば他科の研修も可能。 |
|
| 3年目 | 卒後5年目 | 一人で診断、治療まで完結でき、外来を通して疾患の経過を学ぶ。 |
|
| 4年目 | 卒後6年目 | チームの中核とし、後輩の指導にあたる。また、最短での内科専門医取得を目指す。 | 内科専門医 |
| 5年目 | 卒後7年目 | 各種専門医の取得に向け、専門性を高めていく。 | 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医 |
| 6年目 | 卒後8年目 | 病棟チームのリーダーとして、統括していく。 | 糖尿病内科領域専門医 |
| 7年目以降 | 卒後9年目以降 | 病棟医長、外来医長等の役職に任命され、診療科の中心として運営を担っていく。 | 医学博士 |
診療科入職案内
募集要項
次の9内科共通です。血液内科、呼吸器内科、リウマチ膠原病科、消化器内科・肝臓内科、内分泌内科・糖尿病内科、神経内科・脳卒中内科、腎臓内科、総合診療内科、感染症科・感染制御科
診療科説明会
特に診療科説明会は設けておりません。見学にお越しいただき、当科のことを説明させていただきます。
基本情報
| 医師数 | 27名 |
| 指導医数 | 7名 |
| 病床数 | 26床 |
| 外来診療単位 | 55単位 |
| 入院患者数 | 延べ1,068人 |
| 1日外来平均患者数 | 122.4人 |
| 年間外来延べ患者数 | 35,857人 |
| 年間新患数 | 857人(総合診療内科・病院診療部への受診は含まない) |
| 内分泌負荷試験総数 | 約90件 |
| 主な疾患の内訳 |
高血圧、脂質異常症、高尿酸血症・痛風、糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病など)、糖尿病ケトーシス・ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態、低血糖症・昏睡、肥満症、下垂体腺腫、下垂体機能低下症、先端巨大症、Cushing病、プロラクチノーマ、TSH産生下垂体腺腫、尿崩症、甲状腺機能亢進症、甲状腺クリーゼ、粘液水腫性昏睡、甲状腺腺腫・腫瘍(穿刺吸引細胞診)、Cushing症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、副腎腫瘍、副腎皮質機能低下症、副腎クリーゼ、骨粗鬆症など
|
お問い合わせ
診療科メンバーからのメッセージ
専攻医インタビュー
醍醐味・やりがいは
自分が直接治療方針決定を
行うところ
自分が直接治療方針決定を
行うところ
H先生
2022年入職
(2020年埼玉医科大学卒)
2022年入職
(2020年埼玉医科大学卒)

醍醐味や目指す医師像
専攻医の醍醐味・やりがいは、自分が直接治療方針決定を行うところにあると思います。
初期研修医の頃はどうしても上級医の先生から治療法を学び取ることが中心でしたが、専攻医からは病棟業務に加え本格的な外来業務も開始となり、より患者さんとの距離は近くなります。
自分の方針で患者さんが回復していく場面に立ち会えると非常にやりがいを感じます。また、自分は学生・初期研修医の時にお世話になった先生に「名医」ではなく「良医」になれとご指導をいただき、これを目指す医師像としています。これを達成すべく、内分泌・糖尿病領域の疾患の診断・治療はもちろんのこと、内科領域全般の知識を少しでも高められればと思っています。
初期研修医の頃はどうしても上級医の先生から治療法を学び取ることが中心でしたが、専攻医からは病棟業務に加え本格的な外来業務も開始となり、より患者さんとの距離は近くなります。
自分の方針で患者さんが回復していく場面に立ち会えると非常にやりがいを感じます。また、自分は学生・初期研修医の時にお世話になった先生に「名医」ではなく「良医」になれとご指導をいただき、これを目指す医師像としています。これを達成すべく、内分泌・糖尿病領域の疾患の診断・治療はもちろんのこと、内科領域全般の知識を少しでも高められればと思っています。


内分泌内科・糖尿病内科を選んだ理由
学生時代から漠然と内分泌内科領域に興味があり、これに加え糖尿病は様々な疾患の発症・重症化のリスクであるものの、糖尿病自体を良好にコントロールすることで間接的に重大な疾患を抑制できる可能性がある点からこの領域を専攻することに決めました。また、当科は専門領域はもちろんのこと、自分のやりたいことを第一優先に考慮してくださることや、ワークライフバランスも良いことなども入職理由になりました。
入職して良かったこと
当科は非常に症例数が多く、糖尿病はもちろんのこと内分泌疾患の症例も多数経験できました。専門医を取得する上での内科領域のCommon diseaseを幅広く経験することも可能でした。学会発表体制や教育体制も万全であり、指導医の先生からのフィードバックもしっかりと受けられます。また、ワークライフバランスも良く産休・育休取得も盛んです。これに加え自分の興味のあることを第一優先に行うことのできる科で、皆様のご協力もあり抗菌薬適正使用支援チーム(AST)に参加させていただいたりと、充実した専攻医生活を送ることができています。
初期臨床研修医や医師の方へのメッセージ
当科は症例数も多く、内科専門医取得・サブスペシャリティ取得に必要な症例を十分に経験することが可能です。内科専門医取得の為の制度は確かに楽なものではありませんが、この圧倒的な症例数で申し分ない経験ができると思います。また、当科では糖尿病を始めとして内分泌の希少疾患まで非常に密度の濃い研修が可能です。少しでも興味をもっていただけたら幸いです。皆様と一緒に働けることを楽しみにしています。
プログラムスケジュール
| 年次 | 研修先の病院名、診療科、特に注力する研修等 | 論文、院外活動、他 |
| 医師3年目 | 埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科で研修 | 日本糖尿病学会関東甲信越地方会で発表。病棟に加え本格的な外来業務が始まる。 |
| 医師4年目 | 埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科、小川赤十字病院 内科で研修 | 日本内分泌学会で発表、ASTに参加させていただく、日本感染症学会東日本地方会で発表。小川赤十字病院で内科研修を行う。 |
| 医師5年目 | 埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科、埼玉医大総合医療センター総合診療内科/感染症科・感染制御科で研修 | 子供が産まれ育休を取得させていただいた。感染症に興味があり感染症内科に出向させていただいた。 |
1日のスケジュール
| 8:00 | 出勤(カンファレンスの日) | 内分泌ホルモン負荷試験がある日、カンファレンスの日は出勤し検査、カンファレンスに参加します。 |
| 9:00 | 出勤(通常の日) | 検査のない日は9:00に出勤し当直帯の先生から申し送りを受けます。 |
| 10:30 | 午前中の病棟業務 | 入院患者さん、併診患者さんの状態・検査データ・血糖を把握し、薬剤調整を行います。治療方針はチームで共有します。外来のある日はこの時間は外来をしています。教授回診の日はこの時間に参加します。 |
| 12:00 | 昼食 | 科内でチームの先生と摂ることが多いです。この間に午後の定期入院の患者さんの把握・大まかな治療方針の確認を行うことが多いです。 |
| 14:00 | 定期入院の患者さんの受け入れ | 午後の患者さんの入院対応、診察、検査・治療決定を行います。 |
| 16:00 | 甲状腺穿刺吸引細胞診 | 甲状腺腫瘍の生検検査のある日はこの時間に行います。自分ではないですが副腎静脈サンプリングを行うチームもあり、月2回程度午後の時間にカテーテル検査も自科で行っています。 |
| 17:00 | 午後の回診 | 1日の動きをチームで共有し、当直帯の先生に申し送りを行います。診療科会がある日はこの時間に参加します。 |
| 17:30~18:30 | 退勤 |
主な経験症例とおよその経験数
平均担当患者数- 8人
経験症例
- 1型糖尿病、2型糖尿病
- 原発性アルドステロン症、Cushing症候群、褐色細胞腫
- 尿崩症、下垂体腺腫
- バセドウ病、橋本病、亜急性甲状腺炎、薬剤性甲状腺機能異常
- 肺血栓塞栓症、COPD急性増悪等(出向中に経験)



