腎臓内科
研修可能なサブスペシャリティー領域
以下の各機構・学会の専門医・認定医の取得が可能腎臓専門医(機構認定(予定))、 透析専門医(学会認定)
診療部長等からのメッセージ
私たちは腎臓内科を腎臓病患者を対象とする総合内科と捉えており、教室員は腎臓病や透析療法のスペシャリストのみならず、あらゆる合併症のプライマリーケアを担当するジェネラリストを目指しています。
そこで当科では、血圧や体液電解質管理、腎炎・ネフローゼの腎生検診断・免疫抑制療法やバスキュラーアクセスに対するPTA、そして豊富な他科コンサルテーションなどの院内での専門研修に加え、国際医療センターの腎臓内科(同じ教室)では急性腎障害や多臓器不全の管理も経験できます。
さらに他臓器の合併症に関しても、他科依頼の前にまずは自分たちの問題として考えるという総合内科的な姿勢を大切にし、病棟カンファレンスでは教授から助教までが活発な意見交換を行っています。
ぜひこのユニークな教室の一員となって、一緒に腎臓内科学の広い裾野から高い頂きを目指しましょう。
そこで当科では、血圧や体液電解質管理、腎炎・ネフローゼの腎生検診断・免疫抑制療法やバスキュラーアクセスに対するPTA、そして豊富な他科コンサルテーションなどの院内での専門研修に加え、国際医療センターの腎臓内科(同じ教室)では急性腎障害や多臓器不全の管理も経験できます。
さらに他臓器の合併症に関しても、他科依頼の前にまずは自分たちの問題として考えるという総合内科的な姿勢を大切にし、病棟カンファレンスでは教授から助教までが活発な意見交換を行っています。
ぜひこのユニークな教室の一員となって、一緒に腎臓内科学の広い裾野から高い頂きを目指しましょう。
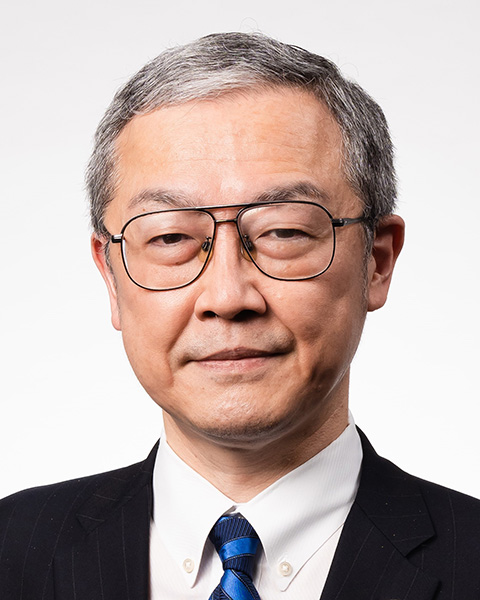 腎臓内科診療部長・教授
腎臓内科診療部長・教授岡田 浩一
研修プログラム
研修プログラムの詳細は領域別専門医研修プログラムのページをご覧ください。概要・特徴
腎臓内科では、検尿異常などのごく初期の腎疾患から腎代替療法(透析・移植)の導入以後まで、全ての病期の腎疾患を診療対象としています。当科は埼玉県南西部における腎疾患診療の拠点であり、入院患者の半数以上が緊急入院です。365日24時間体制で患者を受け入れ、外来部門、病棟部門、血液浄化ユニットが一体となり高度な医療を提供しています。当科の一押し
腎臓内科としては全国でトップクラスの症例数およびその多彩さにつきます。最近の診療実績を例に挙げれば入院患者数700人、腎生検件数80件、透析新規導入数150人、アフェレーシスおよび持続的血液浄化200件(いずれも年間の概数)であり、急性腎障害、慢性腎臓病のあらゆる疾患を経験することができます。また、バスキュラーアクセス専門医により、内シャント造設術100件、PTA150件とバスキュラーアクセス関連の手術も多数おこなっております。また、当科では実地臨床での診療能力を身につけるのと同時に、臨床研究能力を身につける事も重要と考えており、内科学会関東内科地方会、日本腎臓学会東部学術集会、日本透析医学会での症例報告を行っています。
研修内容と目標
| 専門研修 | 卒後年数 | 研修内容と目標 | 資格等 |
| 1年目 | 卒後3年目 | 内科専門医研修・腎臓専門医連動研修(上限あり)・透析専門医研修 | JMECC |
| 2年目 | 卒後4年目 | 内科専門医研修・腎臓専門医連動研修・透析専門医研修 |
|
| 3年目 | 卒後5年目 | 内科専門医研修・腎臓専門医連動研修・透析専門医研修 |
|
| 4年目 | 卒後6年目 | 腎臓専門医研修・透析専門医研修 | 内科専門医 |
| 5年目 | 卒後7年目 |
|
腎臓専門医・透析専門医 |
| 6年目 | 卒後8年目 |
|
|
| 7年目以降 | 卒後9年目以降 |
|
医学博士 |
診療科入職案内
募集要項
次の9内科共通です。血液内科、呼吸器内科、リウマチ膠原病科、消化器内科・肝臓内科、内分泌内科・糖尿病内科、神経内科・脳卒中内科、腎臓内科、総合診療内科、感染症科・感染制御科
診療科説明会
特に診療科説明会は設けておりません。見学にお越しいただき、当科のことを説明させていただきます。基本情報
| 医師数 | 18名 |
| 指導医数 | 4名 |
| 病床数 | 46床 |
| 1日平均外来患者数 | 104名 |
| 1日平均入院患者数 | 43名 |
| 過去3年間の入職実績 | 6名 |
お問い合わせ
診療科メンバーからのメッセージ
専攻医インタビュー
成長の機会が多く与えられる
環境だと感じます
環境だと感じます
O先生
2023年入職
(2019年東京医科大学卒)
2023年入職
(2019年東京医科大学卒)

醍醐味や目指す医師像
日々多くの症例が集まり経験できることで自身の医師としての手札が強制的にでも増えていくことです。腎臓【内科】ですがカテーテル処置やシャント関連などの処置も適度にあるので、手技の手札も増えていくと思います。最終的に対応力に優れた医師を目指したいのですが、それに関してはまだまだ修行中の身です。
腎臓内科を選んだ理由
自主自学があまり得意ではなく専攻医になってから自分の判断と責任で医療行為を進めていくことに不安を感じていた時に研修でラウンドしたことがきっかけでした。
上の科員の先生方が積極的に教育やサポートをする風習が根付いており、この環境なら強制的にでも成長できると感じたからです。(加えて科内の雰囲気が圧迫感や威圧感と縁遠いので、上司に怒られる!といった類の恐怖感が薄かったのもあると思います/勿論これは違う!といった振る舞いをしてしまった場合はちゃんと注意してくれます)
上の科員の先生方が積極的に教育やサポートをする風習が根付いており、この環境なら強制的にでも成長できると感じたからです。(加えて科内の雰囲気が圧迫感や威圧感と縁遠いので、上司に怒られる!といった類の恐怖感が薄かったのもあると思います/勿論これは違う!といった振る舞いをしてしまった場合はちゃんと注意してくれます)
入職して良かったこと
次にとるべき順序や勉強方法がわからなくなってしまった時に、周囲の医師に聞きやすい環境だと感じます。
診療科特有の雰囲気なのか、相手が忙しい時に質問をしても怒ったり迷惑な顔をする医師は皆無です。皆積極的に教えようとしてくれます。
また緊急入院などでどうしても手と時間が足りない時、周囲の科員がいつのまにか集まってきてオーダーや処置を手伝ってくれることが多いのも特徴です。一人で孤立してしまうことはまずありません。
診療科特有の雰囲気なのか、相手が忙しい時に質問をしても怒ったり迷惑な顔をする医師は皆無です。皆積極的に教えようとしてくれます。
また緊急入院などでどうしても手と時間が足りない時、周囲の科員がいつのまにか集まってきてオーダーや処置を手伝ってくれることが多いのも特徴です。一人で孤立してしまうことはまずありません。
初期臨床研修医や医師の方へのメッセージ
当科の強みや雰囲気は一度体験してもらうと非常に実感しやすいと思いますので、怖がらずに一度ぜひ研修にいらしてください。
一見他の診療科に比べると緩めの雰囲気に感じるかもしれませんが、有事の際は雰囲気はそのままに勢いよく実働に飛び込んでいく科員の様を一度見ていただきたいです。
一見他の診療科に比べると緩めの雰囲気に感じるかもしれませんが、有事の際は雰囲気はそのままに勢いよく実働に飛び込んでいく科員の様を一度見ていただきたいです。
プログラムスケジュール
| 年次 | 研修先の病院名、診療科、特に注力する研修等 | 論文、院外活動、他 |
| 医師3年目 | 埼玉医科大学病院 腎臓内科 | 東部腎臓学会発表 |
| 医師4年目 | 埼玉医科大学病院 腎臓内科 | 透析学会発表 |
1日のスケジュール
| 7:45 | 出勤 | |
| 08:00(月・火のみ) | 全体カンファレンス | 教授も含め、科員全体ですべての入院患者の治療内容や方針の確認をします。 |
| 9:00 | 病棟業務開始(初診担当の日は外来) | 血液検査や画像検査の結果を確認します。 |
| 10:00 | (カテーテル留置等がある場合)処置 | 周りに医師が多くいるので、外来日などは助力を求めることも多いです。 |
| 10:30前後(火曜日) | 腎生検カンファレンス | 腎生検の結果を当科教授と病理科の医師とともに確認することができます。 |
| 12:00 | 昼休憩 | |
| 14:00 | 入院患者対応 | 当日の入院患者にムンテラ等をおこないます。 |
| 17:30ー18:15 | 退勤 | 回診とチームで簡易的に患者の振り返りをしたら終了です。 |
主な経験症例とおよその経験数
平均担当患者数- 6-8人
経験症例
- IgG4関連疾患
- ANCA関連血管炎
- うっ血性心不全
- 末期腎不全
- 多発性骨髄腫


