精神科
研修可能なサブスペシャリティー領域
以下の各機構・学会の専門医・認定医の取得が可能日本専門医機構精神科専門医、日本精神科救急学会認定医、日本てんかん学会専門医、日本児童青年精神医学会認定医、日本老年精神医学会専門医、 日本認知症学会専門医、子どものこころ専門医機構専門医、日本総合病院精神医学会専門医、日本臨床神経生理学会(脳波分野)専門医
プログラム責任者からのメッセージ
当科は精神科3次救急や身体合併症も受け入れる常時対応型施設として、県内で重要な役割を果たしています。
精神科救急、気分障害、てんかん、児童青年期・神経発達症、認知症・老年期を5つの柱としており、精神保健指定医のほか各種専門医を取得できます。
光トポグラフィー、てんかんビデオ脳波、無けいれん電気通電療法、反復経頭蓋磁気刺激療法等の特殊な検査・治療をも行える環境で、精神科医としてバランスよく成長できます。
精神科救急、気分障害、てんかん、児童青年期・神経発達症、認知症・老年期を5つの柱としており、精神保健指定医のほか各種専門医を取得できます。
光トポグラフィー、てんかんビデオ脳波、無けいれん電気通電療法、反復経頭蓋磁気刺激療法等の特殊な検査・治療をも行える環境で、精神科医としてバランスよく成長できます。

精神科 診療部長・教授
松尾幸治
研修プログラム
研修プログラムの詳細は以下をご覧ください。概要・特徴
本研修プログラムの特徴は、基幹施設を中心として、我が国の実地臨床で遭遇するケースを網羅的にバランスよく体験できることである。その網羅性は、広さと深さを両立している。1.基幹施設での研修
基幹施設である埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科は2病棟78床と大学病院としては規模が大きく、一つは精神科救急入院料を算定する高規格の専門病棟、もう一つも精神科急性期医師配置加算を算定し精神身体合併症医療等に対応する専門的な病棟である。埼玉県内の精神科医療救急医療体制において重要な役割を果たしており、精神身体合併症患者の24時間365日常時対応施設として県内唯一の指定を受けている。こうした「最後の砦」としての役割を若手からベテランに至るまでが能動的な気概をもって受け止めている。
その姿勢が、当科における診療の広さ、そして表面的に流されぬ深さに繋がっている。治療抵抗例にも積極的に対応する気分障害専門外来、きめ細かな診療が求められる児童青年期専門外来、大学病院精神科では稀なてんかん専門外来等を精力的に展開しているのも、こうした姿勢に由来している。なお当科では重症例のみならず、軽症~中等症の一般的な症例も子供から高齢者まで幅広く診療しており、将来医院開業を検討している医師に必要な研修も十分行うことができる。
2.連携施設での研修
本プログラムの連携施設は多彩である。埼玉医科大学総合医療センターでは、コンサルテーション・リエゾンや一般外来を主体とした幅広い外来中心の診療が体験できる。埼玉医科大学国際医療センターでは、精神腫瘍科において癌患者およびその家族の精神的ケアを体験することができるほか、救命救急センターにおけるコンサルテーション・リエゾン診療を通じて自殺企図症例等への対応を経験できる。当院と同じ敷地内にある丸木記念福祉メディカルセンターでは、慢性期の精神疾患、認知症疾患医療センター、重症心身障害、などの診療が体験できる。県立精神医療センターでは、医療観察法病棟での診療、薬物依存の専門診療など、大学病院では学び難い症例を経験出来る。※他詳細は「研修施設群と研修プログラム」の項を参照
診療科入職案内
募集要項
1次選考日:2025年11月18日(火)18:00~2次選考日:2025年12月19日(金)17:00~※
3次選考日:2026年 1月30日(金)16:00~※
※なお採用予定者が募集人数に到達した時点で以降の募集は停止となります。
診療科説明会
診療科説明会のご案内は、当科ホームページの「お知らせ」(https://saitama-med-psy.jp/)に概要が整い次第掲載してまいります。また、病院見学やZOOM面談等も随時受け付けておりますので、同じく当科ホームページの「見学のご案内」(https://saitama-med-psy.jp/recruit/)をご参照ください。基本情報
| 医師数 | 26名 |
| 指導医数 | 5名 |
| 病床数 | 78床 |
| 1日平均外来患者数 | 126名 |
| 1日平均入院患者数 | 56名 |
| 過去3年間の入職実績 | 13名 |
| 連携施設数 | 14施設
【連携施設名等】:「研修施設群と研修プログラム」 ①埼玉医科大学総合医療センター:コンサルテーション・リエゾンや一般外来を主体とした外来中心の診療を幅広く体験でき、認知行動療法等の各種精神療法につき理解を深めることができる。 ②埼玉医科大学国際医療センター:癌患者のせん妄からこころのケア、さらには遺族外来に至るまでサイコオンコロジー全般につき貴重な体験ができるほか、救命救急センターでのコンサルテーション・リエゾンを通じ重度の自殺企図症例への対応が経験できる。 ③丸木記念福祉メディカルセンター:慢性期精神疾患の社会復帰・リハビリテーション・多職種連携や認知症疾患医療センターとしての活動も見聞できるほか、重症心身障害施設における診療も体験できる。 ④県立精神医療センター:医療観察法病棟における入院処遇対象者の診療や、アルコール・薬物依存症の専門的な診療等の貴重な経験ができる。 ⑤社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター:県央精神科救急医療の一翼を担うほか、認知症や他の神経変性疾患の診療を積極的に展開しており、こうした神経疾患の精神症状治療について経験できる。 ⑥都立松沢病院:我国で代表的な精神科病院で東京都の行政精神科医療で中核的な役割を担っており、精神科救急、身体合併症、医療観察法、薬物依存症から社会復帰・リハビリテーションに至るまであらゆる領域を経験することができる施設である。 ⑦福岡大学病院:地域の中核的な総合病院でもあり、身体合併症やコンサルテーション・リエゾン等につき経験できるほか、精神分析的療法等につき学ぶ環境が充実している点が特徴である。以下の精神科病院・医院は地元の地域精神医療を担い設立者の臨床哲学に応じた特色ある診療を行っており、貴重な体験ができる。 ⑧三信会岸病院、⑨碧水会汐ヶ崎病院、⑩松風荘病院、⑪つむぎ診療所、⑫西熊谷病院、⑬東松山病院、⑭武蔵の森病院、 |
お問い合わせ
診療科メンバーからのメッセージ
専攻医インタビュー
研究をしながら
精神科専門医・精神保健指定医を
同時に取得したのち
学位も取得しました
精神科専門医・精神保健指定医を
同時に取得したのち
学位も取得しました
K先生
2018年入職
(2016年埼玉医科大学卒)
2018年入職
(2016年埼玉医科大学卒)
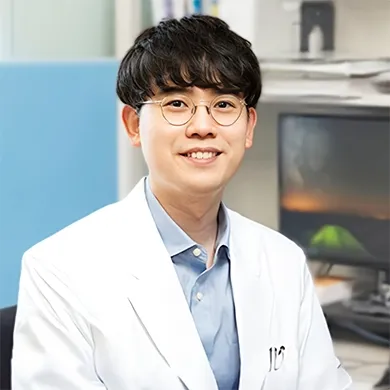
醍醐味や目指す医師像
当科は専攻医1年目から主担当医として患者さんの診療に携わることができるため、非常にやりがいがある環境です。まだ一人前ではないという不安もありますが、上級医が常にサポートをしてくれるため安心して成長できたと感じています。また、身体合併症を抱える患者さんの内科的管理にも関わることができ、幅広い医学知識を学べます。患者さんに寄り添える真に信頼される医師を目指し、日々精進しています。

神経精神科・心療内科を選んだ理由
当科は大学病院で数少ないスーパー救急病棟を有し、地域の基幹病院として精神科領域の軽症例から最重症例まで幅広い疾患に対応できる点に魅力を感じました。
さらに、入院患者が退院後も自身の外来で診察を続けられるため、精神科医としての実力を確実に身につけられると考えました。また、診療をしながら研究にも携われるため、当科を選択しました。
さらに、入院患者が退院後も自身の外来で診察を続けられるため、精神科医としての実力を確実に身につけられると考えました。また、診療をしながら研究にも携われるため、当科を選択しました。
入職して良かったこと
当科の雰囲気は良いと聞いていましたが、実際に入職してみると、予想以上に上級医の先生方が親切で、教授の先生方とも気軽に相談できる環境であることに感動しました。そのおかげで、当科が専門としている「精神科救急」「気分障害」「神経発達症」「てんかん」「認知症」の分野において幅広く知識を深めることができています。
初期臨床研修医や医師の方へのメッセージ
当科は、埼玉県の精神科医療の中心的な役割を担う病院の一つとして、幅広い診療を行っています。やりがいのある環境の中で、確実に力をつけることができます。
私たちと一緒に、精神科医療の現場で経験を積みながら、一緒に成長していきましょう。皆さんと共に働ける日を楽しみにしています。
私たちと一緒に、精神科医療の現場で経験を積みながら、一緒に成長していきましょう。皆さんと共に働ける日を楽しみにしています。
プログラムスケジュール
| 年次 | 研修先の病院名、診療科、特に注力する研修等 | 論文、院外活動、他 |
| 医師3年目 | 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 | |
| 医師4年目 | 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 | 初めての学会発表 |
| 医師5年目 | 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科/丸木記念福祉メディカルセンター | 研究活動,学会発表(専門医研修中の医師による演題で優秀発表賞取得) |
| 医師6年目 | 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 | 精神保健指定医・専門医取得に向けてレポート作成、学位論文作成 |
| 医師7年目 | 埼玉医科大学病院 神経精神科・心療内科 | DPAT活動 |
1日のスケジュール
| 8:30 | 出勤 | |
| 9:00 | 外来 | 外来新患の予診をおこない、その後に上級医の本診を見学。新患症例について検討も行います。 |
| 12:00 | 昼休憩 | |
| 13:00 | 病棟 | 入院患者さんの診察、病棟スタッフと情報を共有します。困ったら上級医と相談を行います。 |
| 15:00 | 往診・新入院対応 | 往診や新入院の対応等、臨機応変に対応します。 |
| 17:30 | 自己研鑽 | 必要に応じて自己学習や研究活動を行います。 |
| 19:00 | 退勤 |
主な経験症例とおよその経験数
平均担当患者数- (専攻医3年目)入院受持:5-6人/日(延べ:30-40人/年)、外来 10-20人/週
経験症例
- 統合失調症 30人前後
- 気分障害 30人前後
- 神経症性障害,ストレス性障害等 50人前後
- 児童・思春期精神障害 10人前後
- 精神作用物質使用による精神障害等 10人前後
- 器質性精神障害 20人前後
- 成人のパーソナリティ障害等 5人前後
- てんかん 10人前後
- 睡眠障害 10人前後

