Our Professional Stories
埼玉医科大学 臨床工学科
副学科長 山下 芳久 先生
埼玉医科大学 臨床工学科
副学科長 山下 芳久 先生
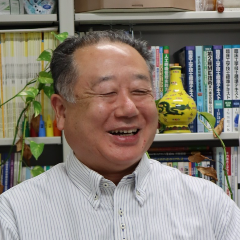
病院内の先端医療機器の操作で治療をアシストする臨床工学技士は、医療機器のメンテナンスから生命維持システムの管理まで、先端医療を支える必要不可欠な役割を担っています。山下 芳久 先生は、臨床工学技士の国家資格ができる前から臨床工学技士が現在行っている業務に携わってこられました。山下先生は、埼玉医科大学病院 中央機材室や腎臓病センター、血液浄化部の立ち上げなどに関わり、今では、日本臨床工学技士会(臨床工学技士の数 41,533名)の副理事長として、臨床工学技士の医療安全や領域拡大、卒前教育、国際交流等の委員会を統括しておられます。臨床工学技士のはじまりをよく知る山下先生にお話を伺いました。
体育好きでジェームズ・ボンドに憧れる幼少期
――運動大好きで体操選手を目指す
小さい頃は、体育が大好きでした。忍者にジェームズボンド(映画007の主人公)に憧れていました。実家の裏にあった田んぼで、前宙返りや後ろ宙返りをよく練習していましたね。中学校では体操部に入って、将来、オリンピックに出ることに夢を描いていたんです。ところが、私の通う中学校では体操部はなかったもので、当時、埼玉県の県大会で優勝していたバスケットボール部に入りました。
――2つの苦手を克服
運動は大好きだったんですが、中学進学時の私の身長は140cm、体重は29 kgだったんです。体も細くて体力もなかったですね。当時はご飯も全然食べられなくて、、、これは良くないと思って、中学校の時に好き嫌いをなくしました。また、私はあがり症だったんです。バスケットボールの練習では何でも上手く行ったんですが、試合になると全然ダメでした。心臓がバクバクしちゃって、、、今でも覚えていますが、最初の試合で2ゴール、4得点で惨敗しちゃったんです。ここでも、これは良くないと思って、強い心を持ってバスケットボールをやって、あがり症を克服できるようになったんです。それから25歳くらいまでバスケットボールを続けて、全国青年大会の埼玉県代表のキャプテンを務めるまでになりました。
臨床工学技士になるまで
――医学電子科での学生生活
体育以外ではやっぱり理科や数学が好きだったんです。一番興味あるのは生命(いのち)であり、人体の構造だったんです。そして、当時はエレクトロニクスが全盛でしたので、医学と電子が学べる東京電子専門学校の医学電子科で医療と電子を学びました。学生実験レポートはとても大変でしたね。100枚くらいのレポートを書いて、今では考えられないですよね。毎回、徹夜してレポートを書いてました。これが一番の思い出ですね。
――川越の赤心堂病院に務める
医学と電子を勉強していたので、医療機器メーカーか病院に勤めるのが一般的でした。病院では心電図や脳波などの生理検査もしくは血液透析をやっていて、私は血液透析で治療に関わることができる赤心堂病院に入職しました。1981年当時は臨床工学技士の国家資格はなかったので、透析技術員として血液透析に携わっていました。当時、病院の中では無資格者は肩身が狭くて、悔しい思いもたくさんしました。それを糧に勉強をたくさんしていました。
――問題も多かった1980年代の血液透析
この頃の血液透析は問題も色々あって、透析後半に患者状態が悪くなってしまうことも度々ありました。患者さんはショックを起こしたり、心停止などを起こすので、心臓マッサージなども経験しました。さらに、その頃は装置の不良もたくさんありましたから、次の日、血液透析を行うためにメンテナンスも徹夜で行うなんてこともありましたね。もちろん、今の血液透析装置は技術が向上していますから、そんなことは滅多にありません。
――臨床工学技士になるより先に技士長(責任者)になっちゃった
赤心堂病院には先輩も多かったのですが、不思議な縁で、、、4年目にして技士長(責任者)を任されました。入職してから医療の壁にもぶつかって、ちゃんとしたカリキュラムに載って勉強しなければならないなと思い、西武医学技術専門学校 臨床検査技師科の夜間部に通って基礎医学を勉強しました。私は、いずれ設置されるであろう臨床工学技士の国家資格のために、今は基礎医学を学んでおきたいという想いで臨床検査の課程を借りたんです。臨床検査技師は検査がメインで、臨床工学技士のように治療には携われないですからね。病院内に続々と登場する先端医療機器の担い手として、医師や看護師では手が足りないですから。先端医療機器を扱う国家資格がきっとできるだろうという想いを胸に秘めて日々の業務に勤めてきました。それから3年後の1988年、国家資格 臨床工学技士が制定されたんです。そして、私は、第一回 臨床工学技士国家試験に合格し、臨床工学技士になりました。
埼玉医科大学病院で
――色々やってやろう!
赤心堂病院は、当時の埼玉県内の血液透析の症例数も多く非常に有名だったんです。ただ、血液透析だけだったんですね。血漿交換(体の外に取り出した血液を血漿分離器で血球と血漿成分に分離した後、廃棄した患者さんの血漿を健常な方の血漿で置き換える治療)、アフェレシス(体外循環によって血液中から病気の原因となる因子を除去する治療のこと)、機器管理や人工心肺などはやっていなかったんですね。それらをできる病院は、やっぱり大学病院を有する埼玉医科大学しかなかったんです。ただ、その頃、知り合いの方に声をかけられて、血液透析のクリニックの立ち上げも経験しました。そのクリニックは、お年を召した方が多かったんです。お年寄りの穿刺は簡単ではなくて、そこで穿刺技術も学びました。色々な経験をして、1990年に埼玉医科大学病院に入職することになりました。
――中央透析室を改革する
当時の埼玉医科大学病院には,臨床工学技士として見目 恭一 先生(埼玉医科大学 名誉教授・元 臨床工学科 教授)がMEサービス部におられて、人工心肺業務を指揮されていました。「私も見目先生と一緒に働ける!最高だなぁ」と思ったんですね。それが、入職してみたら、私だけ中央透析室に配属されちゃったんです。そのとき、中央透析室にいる臨床工学技士は私一人でした。大学病院の透析室だから非常にレベルが高いと思ったんですが。。。当時の中央透析室のレベルはそれほど高くなかったんです。そのときから中央透析室の改革が始まりました。看護師さんを集めて勉強会を開きました。穿刺の仕方、抗凝固薬の使い方、プライミングの方法などを教えました。ただ、臨床工学技士は私一人だけでしたから毎年少しずつ臨床工学技士を採用するようにしたんです。
――日本初期!医療機器の中央管理
中央透析室に勤務してから2年後、私は病院長命を受けて中央機材室の立ち上げを日本全国に先駆けて行うことになりました。当時、病院のたとえば人工呼吸器は医局のお金で購入していたのですが、これを中央管理しようという病院長の指示の下、大改革を行いました。こういった試みは日本で最初の方で。どこもやっていない画期的内容だったので、その後で東京女子医大、自治医大など色々な大学病院からも見学に来られました。そのとき、病院長に看護部から独立した臨床工学技士の所属部門の立ち上げをお願いしたんです。
――腎臓病センターの立ち上げと血液浄化部の発足
ある日、高度な血液透析を行うために、慶應義塾大学病院から医師を招いて腎臓病センターを立ち上げるというお話を理事長からいただいたんです。立ち上げるといっても血液透析室の設計が必要ですから、どういう機材がいるのか、配管はどうするのかって。そこで、大阪の病院に見学に行くのに理事長に同行させていただいたこともあるんです。そして、1994年10月31日になんとか開設にこぎ着くことができました。出口 修宏 先生、鈴木 洋通 先生たちが臨床工学技士に理解を示してくださったので、医師と臨床工学技士でタッグを組んで、臨床・教育・研究をバンバンすることができたんです。研究発表は20年間で500演題、150本もの論文も発表してきました。開設時に臨床工学技士として入職してきたのが、本学科の三輪 泰之 先生(講師)や国際医療センターMEサービス部におられる塚本 功 さん(現 課長補佐)なんです。1999年には臨床工学技士の独立部署として血液浄化部も立ち上げました。このときには、16人の臨床工学技士が血液浄化部に配属されていました。それから7年後の2006年、保健医療学部が開設され、臨床工学技士を養成する医用生体工学科(現 臨床工学科)が立ち上がるんです。私は、臨床現場をもっともっと盛り上げていきたいと思っていたんですが、それ以前の卒前教育もなんとかしていかないといけないと思ったんです。そこで私は臨床工学技士を養成する教員を目指しました。
――日本臨床工学技士会での役割
これまで、日本臨床工学技士会の国際交流委員を務めてきました。2006年に国際交流委員長になったのですが、このとき、日本国際協力機構(JICA)、財団法人国際医療技術交流財団(JIMTEF)から技士会に初めての依頼があって、カンボジアの医療機器の調査に行く機会がありました。カンボジアの病院内の様子は日本と似たような感じだったんですが、スタッフに詳しくお話を聞いてみると、実際には医療の質に大きな差がありました。特に血液透析に使用するダイアライザなんか洗って再使用するような状況で、衛生面での問題が顕著でした。現地の保健省職員、医師、そして、技術者からも直接お話を伺うことができました。その翌年、カンボジアの医療スタッフを日本に招いて、日本の医療現場の研修をしていただきました。これにより、カンボジアの医療の質の向上に貢献する橋渡し役も果たすことができました。実は、海外では、昔も今も…ダイアライザをリユース(再使用)しているんです。これでは透析効率を一定にできません。日本ではとても考えられないような状況で医療が行われているんです。日本の医療の質は非常に高いんです。
未来の臨床工学技士に求めること
――臨床工学技士に起こっているタスクシフトの風
医行為は医師が行うわけですが、ここでいう医行為は、検査・診断・治療の3つに分けることができます。検査と診断は、臨床検査技師や診療放射線技師など色々な職種で実施しています。治療に関わっているのは、医師、看護師、そして、臨床工学技士なんです。高度医療機器の進歩に伴って,今後、ますます医師がやってきた内容がタスクシフトされてくると思うのです。タスクシフトの相手は,医学と工学の知識を備えた臨床工学技士になるはずです。
――臨床工学技士の絶対数はまだまだ足りない
近年、カテーテル治療やロボット支援手術(ダビンチ)といった手術室業務でも先端医療機器の準備や操作を臨床工学技士が任されています。今までの臨床工学技士の主要な業務である血液透析、人工心肺、そして、機器管理といった業務は他の医療職種にタスクシフトされることはありません。だからこそ、臨床工学技士の人数をもっともっと増やしていかなければならないと考えています。また、これからは在宅医療にも臨床工学技士が大きく関わってくるはずです。病院の病床数が限られているものですから、在宅医療もどんどん増加していくと思います。すでに自宅に医療機器を設置されている方もおられますが、それらをちゃんと保守点検・管理する必要があるので、そこでも臨床工学技士が求められています。臨床工学技士が求められる業務内容は、非常に多岐に広がっています。
――未来の臨床工学技士になる高校生に伝えたいこと
私が一番大切にしているのは、「生命(いのち)」です。だからこそ、「いのち」を守ろうという想いを強く抱いてもらいたい。こういっちゃうと、高校生には重く感じられちゃうかもしれません。そして、高校生には、臨床工学はイメージがつきにくくわかりにくいと思う分野かもしれません。それはどんなことでも同じですが、好きになってもらうことで色々変わって見えてくることもあると思うんです。そういったところから、まずは臨床工学技士をぜひ知っていただきたいと思います。臨床工学技士は、医療分野では歴史も浅く、知名度もそんなに高くありませんが、臨床工学技士の働く領域は病院内・外を問わず非常に広がっています。医療の進歩に対応して常に進化しているのが臨床工学技士なのです。