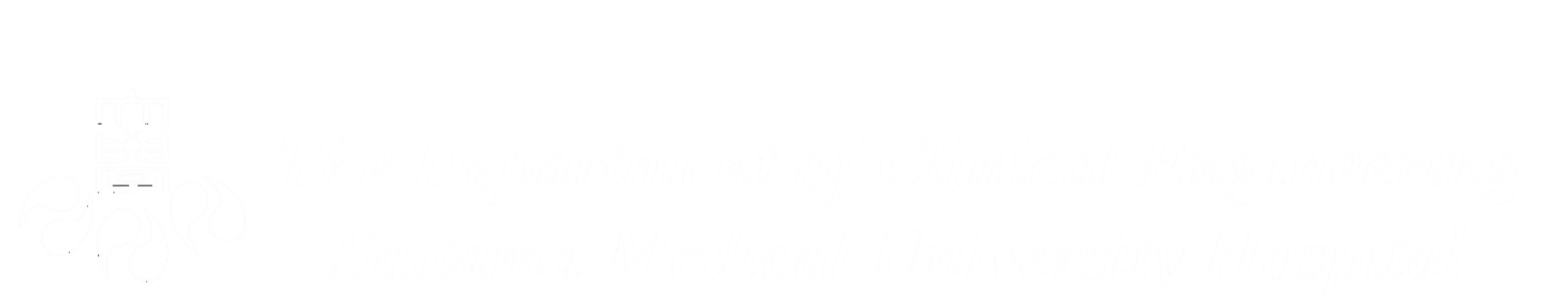中央機器管理業務

概要
2007年4月に厚生労働省から改正医療法が発出され、医療機器を安全に使用するための指針として、以下の4項目が義務付けされています。
①医療機器の安全使用を確保するための責任者(医療機器安全管理責任者)の設置
②従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
③医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
④医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、その他利用機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
医療機器安全管理責任者は医師、看護師、臨床工学技士等であることが条件となっていますが、この役割を担う職種として臨床工学技士が適切との方向性も打ち出されており、医療チームでの期待が大きくなっています。当院では臨床工学技士が医療機器安全管理責任者に任命されています。この指針により、病院内の医療機器保守管理における臨床工学技士の需要は高まり、病院内における 医療機器管理は中央管理下されている施設も多くなっています。
中央機器管理業務とは
院内各署に適した汎用的な医療機器を管理し、貸出管理、保守、環境整備、教育等の業務を行い、臨床現場へ信頼性の高い機器を過不足なく供給すると共に、経済効率性、安全性を高める供給にも応えています。安全使用のために必要となる情報収集を随時行い、医療機器の添付文書および取扱説明書を一元管理しています。また、医療機器不具合情報等の医療機器に関する情報を院内に周知するため、広報紙を毎月作成、発行しています。
臨床工学技士が院内の医療機器の保守管理を行っており、人工呼吸器や除細動器などの生命維持管理装置を含め、稼働している機器は合計1862台(2023年5月時点)になります。
管理方法
医療機器の管理方法として、医療機器の情報を管理ソフトに登録しています。
医療機器の情報として、機器本体の登録の他、不具合対応や修理に関しても管理ソフトに登録し、管理しています。
その他にも管理している医療機器に関する材料や消耗品に関しても管理を行っています。
機器管理台数
合計:1862台(2023年5月時点)
| 人工呼吸器本体 | 60台 | 高流量酸素ブレンダ | 14台 |
|---|---|---|---|
| 生体情報モニタ | 319台 | 心電計 | 27台 |
| 除細動器 | 26台 | AED (自動体外式除細動器) |
54台 |
| 輸液ポンプ | 436台 | シリンジポンプ | 254台 |
| パルスオキシメーター・カプノメータ | 260台 | ネブライザ | 57台 |
| 間欠的空気圧迫装置 | 38台 | 経腸栄養ポンプ | 20台 |
| そのほかの機器 | 331台 |
保守点検
稼動している機器に関して、機器毎に点検予定を立て、定期点検を実施しています。
人工呼吸器や除細動器などの生命維持管理装置に関しては半年に1回、その他の機器は1年に1回、保守点検計画を立てています。
定期点検方法の内容や手技統一の為、各医療機器に対して定期点検手順書を作成しています。
メーカーによる技術講習のある機器は、技術講習会に積極的に参加し、メーカー指定の方法で点検を行っています。
中央管理機器の貸出、返却
中央管理機器は、必要に応じて病棟に貸出しています。病棟で使用された機器は、使用後(1患者1使用)に返却される仕組みとなっており、毎月、貸出・返却作業を延べ3000~3500台程度を行っています。 臨床工学技士は、返却後の清掃・終業点検および貸出準備を実施しています。
終業点検に関しては、点検作業の標準化を図るべく、点検手順書を作成し、それを基に点検を実施しています。
不具合対応
不具合対応では、破損時の対応や動作不良時の対応があります。
破損の場合は院内修理で可能な限り対応し、不能な場合はメーカー修理としています。動作不良の場合、緊急性を要するものは直接現場で出向き、対応をしています。緊急性が低いものは連絡票と共に医療機器を中央機材室に提出してもらい、院内点検(故障点検)を実施しています。
重要性の高い動作不良に関しては原因究明と再発防止に努め、必要に応じ、医療機器メーカーへの情報提供や原因究明要請も行っています。
安全巡回
人工呼吸器
病棟で使用している人工呼吸器に関して、1日1回巡回を行っています。
巡回では各呼吸器の稼働状況や動作状況を確認し、安全使用がなされているかを確認しています。
除細動器、AED(自動体外式除細動器)
各部署へ配置している除細動器、AEDに関して、毎月実施しています。
除細動器では、外装点検や充電状態、備品の確認の他、出力テストを実施し、除細動器が安全に使用できるかを確認しています。
AEDでは外装点検やインジケータ表示の確認、電極パッドの個数・使用期限を含めた備品の確認を行っています。
生体情報モニタ
各部署へ配置している有線式、無線式、セントラルモニタに関して、毎月実施しています。
外装点検や本体の固定状態、アラーム音量や設定などの確認を行っています。また、送信機の管理状態も確認しています。
講習会の実施
2007年4月に厚生労働省から改正医療法「医療安全関連通知」が出され、医療機器を安全に使用するための指針として医療機関に義務付けされた項目の1つに「従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施」があります。また、当院は特定機能病院であるため、特に安全使用に際して技術の習熟が必要と考えられる医療機器に関しての研修を年2回程度、定期的に行い、その実施内容について記載することとされています。
特に安全使用に際して技術の習熟が必要と考えられる医療機器が表の8項目となっています。
特に安全使用に際して技術の習熟が必要と考えられる医療機器
①人工心肺装置および補助循環装置
②人工呼吸器
③血液浄化装置
④除細動器(自動体外式除細動器:AEDを除く)
⑤閉鎖式保育器
⑥診療用高エネルギー放射線発生装置(直線加速器など)
⑦診療用粒子線照射装置
⑧診療用放射線照射装置(ガンマナイフなど)
定期講習会
人工呼吸器や除細動器など、特に安全使用に際して技術の習熟が必要と考えられる医療機器以外にも、輸液ポンプや生体情報モニタなど、医療機器の講習会を実施しています。
講習会は年2回実施しており、講師および講習会資料の作成を臨床工学技士が行っています。
部署別講習会
新しく購入した医療機器、臨床試用機器等、はじめて使用する機器は使用方法や取扱についての講習会を臨床工学技士あるいはメーカーにより実施しています。